昨夏、北海道に初の優勝旗を持ち帰った巨摩大藤巻。その後秋の神宮大会・春の選抜と危なげなく優勝を重ね、三連覇の快挙を成し遂げた。
来たる夏の甲子園での連覇に向けて、「世代最強エース」と名高い投手・本郷正宗(2年)に焦点を当てながら、巨摩大藤巻の強さの真髄に迫る!
巨摩大藤巻の強さの秘密は雪にあり
北海道といえば、雪。冬の厳しい練習を乗り越えて春以降花開かせていく高校球児たちが多い中で、積雪により練習の幅が狭まる雪国の高校は不利とされてきた。そんな逆境を跳ね除け、初の優勝旗の津軽海峡越えに続いて秋春と首位独占状態の巨摩大藤巻。
一度優勝すると、周りの高校はどうにかして打ち負かそうと躍起になってかかってくるものだ。王者にはそれを迎え撃つだけのエネルギーが必要とされる。そんな中で秋の神宮大会も優勝し、さらにマークが厳しくなった春の選抜。なんと巨摩大藤巻は、大会無失点で他を全く寄せ付けない文句なしの優勝を勝ち取った。
その圧倒的な強さの秘訣は、本来ならハンデとなる"雪"を己を磨く糧に変えたことにある。
降り積もった雪を掻き分け、固く凍った氷の上で行う雪上ノック。土のグラウンドに比べてイレギュラーが多く、時には顔面に直撃して出血することもあるのだとか。
同じく北海道の高校で甲子園制覇を成し遂げた巨人・田中将大選手も「怖かったという印象しかない」と自身の動画で語っている。
しかし、それが予想外の動きに対応する反応速度を上げた。
そして何より、恐怖すら覚えるその練習を乗り越え甲子園に現れた彼らの顔つきは自信に満ち溢れている。
「恵まれた環境で練習をしてる奴らには負けない」─マウンドから打者を厳しく攻め立てる本郷の顔はそう物語っているかのようだ。

本郷の強さを引き出す敏腕監督
本郷は打者を威圧し、まるで怒りをぶつけるような迫力のある投球が特徴的だ。しかし、時折ベンチでもその憤りを監督・新田幸造に向けている様子が見られる。あろうことか監督に喰ってかからんとする鋭い眼差しを向けているのだ。

信頼、尊敬、畏怖──選手と監督を結ぶ感情は様々である。しかし、本郷と監督の間にあるのはそのどれとも違うように思えてならない。
新田は本郷について、「苛立ちも不満も負けん気も怒りも、全ての感情を投球で表現できる選手」と話す。
怒りなど負の感情は大きな力にもなり得るが、苛烈さを増すほどコントロールが難しくなり、制球の乱れに繋がる選手も少なくない。そのため、ポーカーフェイスで淡々と投げ込む投手が良しとされることも多い。
しかし、本郷はまさにその逆をいく選手だ。無理に負の感情を抑え込むのではなく、その感情を投球にぶつける。そしてそれが制球を乱すどころかより厳しいところをつく投球へと昇華される。
本郷の稀有な才能を引き出し、巧みに操る老獪な指揮官。まさに鬼に金棒ならぬ鬼と鬼の競演である。
本郷を温存しても勝てる組織力
巨摩大藤巻と言えば本郷のチーム。
そう言われるのも頷ける本郷の活躍ぶりではあるが、もう一つこのチームを表現するのによく使われる表現がある。「継投の巨摩大藤巻」だ。
昨夏の甲子園決勝では関東屈指の左腕・成宮擁する稲城実業(西東京)と激突。試合は延長14回までもつれる接戦となった。最後まで成宮が粘りの投球を見せる稲実に対し、巨摩大藤巻は4人の投手リレーで稲実を翻弄。監督の采配がぴたりとハマり、見事王座を勝ち取った。
春のセンバツ準決勝でも、機動力に定評のある白龍(群馬)相手に本郷を温存して挑み、結果は完封。
世代最強エースを擁しながら、その本郷を温存しても全国屈指の強豪と渡り合える組織力が三連覇の鍵となっている。
そんな巨摩大藤巻の堅実な守備を支えるのが、主将の西秀雄(3年)だ。

セカンドで堅実な守備を見せ、本郷をはじめとした投手陣を後ろから盛り立てる。また、明るい性格でチームのムードメーカーでもある西は、他校の選手と言葉を交わす様子も多い。
無口で堅物な印象の本郷にも気兼ねなく声をかける彼の明るさが、チームを照らしている。
本郷の闘志漲る投球を受け止めるのは捕手・円城蓮司選手(2年)だ。

本郷とは中学時代からバッテリーを組む。荒々しく感情をぶつけるようにプレーする本郷とは対照的に、円城は冷静沈着に本郷をリードする。熱と冷、相反する二人が織りなすピッチングが打者を攻め立てる。
選抜では、準々決勝での降谷擁する青道(西東京)との投手戦で試合を決める2点タイムリー、準決勝の白龍戦では3打点と打撃でも本郷を援護する。
本郷を筆頭に充実した投手陣、冷静に投手をリードする奥義の要、野手陣の中心で明るくチームを鼓舞する主将、そんな選手たち統率する百戦錬磨の智将。
この盤石な布陣を打ち崩し、巨摩大藤巻の四連覇を阻止するチームが現れるか。はたまたこの破竹の勢いそのままに再度優勝旗を奪い去るのか。
北国の猛者が球史に新たな歴史を刻む日はそう遠くないのかもしれない。
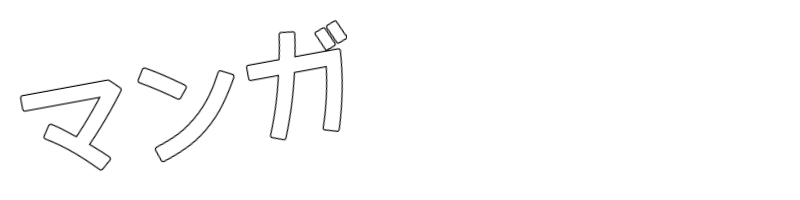

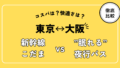
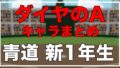

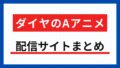



コメント